犬の膵炎にサツマイモは食べさせても大丈夫

膵炎は、原因を特定することが難しい病気ですが、脂肪分の多いフードや人間の食べ物を日常的に食べているワンちゃんにとって発症のリスクが高い病気としても知られています。
膵炎と診断された場合、最も大切なのが低脂肪の食事療法です。
低脂肪食が適切だとわかっていても、これまで脂肪分の多いフードを食べていたワンちゃんの場合、低脂肪の療法食を食べてくれないことが多くあります。
また、好みがはっきりしているグルメなワンちゃんの場合も低脂肪食を嫌がることがあります。
そんな時に役立つ食材がサツマイモです。
ワンちゃんが大好きなサツマイモは、とても栄養豊富な優秀な食材なの一つ。
その甘さからGI値の高い食材と誤解されがちですが、実はサツマイモのGI値は55と玄米よりGI値の低い食品なのです。
この記事では、膵炎のワンちゃんにサツマイモを与えても大丈夫な理由と焼き芋や干し芋は与えても大丈夫なのかなどサツマイモを与える際の注意点について詳しく解説します。
糖尿病を併発している場合は調理法に注意
食物繊維が豊富に含まれているのでカラダにも優しく、また栄養素も豊富で免疫アップ効果も期待できるサツマイモは、膵炎の他に糖尿病を併発しているワンちゃんにも与えて大丈夫な野菜です。
食後の血糖値上昇を防ぐ低GI値食品のサツマイモは、近年、ダイエットフードとして女性たちからも注目を浴びています。
GI値とは、グリセミックインデックスの略で、食後の血糖値上昇を示す値として使用されています。
このGI値が高いほど、食後の血糖値上昇が高く、低い場合は食後の血糖値がゆるやかに上昇することを示します。
膵臓で作られるインスリンは、血糖を一定の範囲に収める働きを担うホルモンの一種で、糖尿病はこのインスリンが正常に働かないために、ブドウ糖が血液中に増えてしまう病気です。
糖尿病を併発すると、インスリンが働かないため血糖値が高くなってしまいます。
ワンちゃんの場合、糖尿病を発症すると食後に急激に血糖値が上昇しないように配慮された繊維質を多く含む療法食が処方されます。
食物繊維が豊富で低GI値のサツマイモは、糖尿病のワンちゃんに与えることができますが、その際には調理法に気をつけなくてはなりません。
サツマイモは、水分を失わないように短時間で加熱することで低GI食品となります。
そのため、蒸す、煮るなど水分を損ねない調理法がカギとなります。
糖尿病を併発しているワンちゃんに与える場合は、長時間加熱して作られる焼き芋や糖分の多い干し芋を避け、蒸すまたは茹でたサツマイモを与えましょう。
犬の膵炎とは
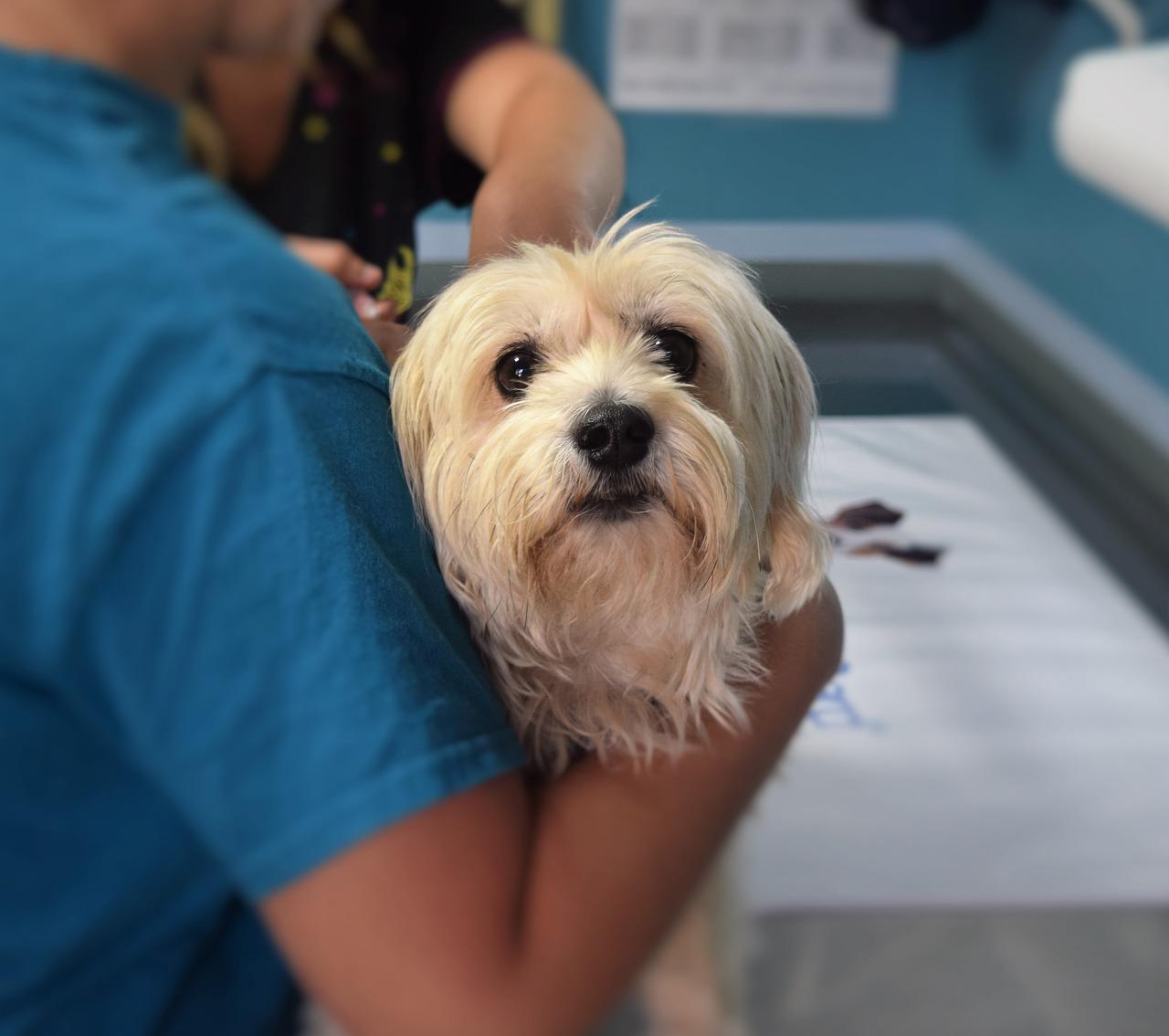
愛犬の食欲がなくなったり、元気がない、嘔吐を繰り返す、お腹を痛がるなどの症状を見せた時に、獣医師から告げられることが多い病気が膵炎です。
以前はメスの高齢犬に発症しやすいとされていた膵炎ですが、最近ではさまざまな要因から年齢に関係なく発症するワンちゃんが増えてきています。
膵臓は、小さいながらも消化吸収に関わる大切な役割を持っています。
膵臓は胃のやや右側、十二指腸の近くにある小さな臓器で、膵液という消化液を分泌している臓器です。
膵液には、血液中の糖分を調節するインスリンなどのホルモンの分泌(内分泌部)とたんぱく質や脂肪を消化する強いアルカリ性の消化液(外分泌部)の2種類の働きがあります。
強い酸性の胃液で消化される途中の食べ物は、十二指腸で膵液によってさらに分解されて小腸に送られます。
膵炎は、犬にとって大切な栄養素を分解する酵素を分泌する膵臓に炎症が起きる病気で、急性膵炎と慢性膵炎の2タイプがあります。
多くのワンちゃんが発症する急性膵炎の初期症状では、腹痛があるため、お腹を触ると痛がる、前脚を伸ばし胸を床につけてお尻を持ち上げた「祈りのポーズ」をする、元気がない、食欲がない、嘔吐を繰り返すなどが現れます。
肥満の犬や高脂肪の食事をしているワンちゃんに多く見られる慢性膵炎では、急性膵炎とよく似た症状が現れますが、膵臓の炎症が持続することで、膵臓が硬くなり、膵臓の機能障害を起こします。
膵臓に炎症が起きる原因はさまざまですが、急性膵炎を発症すると強いアルカリ性の膵液が過剰に分泌され活性化することで、自分の膵臓を消化、結果として膵臓に炎症やむくみ、壊死などが起こってしまうのです。
さらに、膵炎を放置しておくと、高熱や全身の各所に血栓ができる、全身の臓器に炎症が及ぶなどの末期症状が現れ、腎不全や多臓器不全など全身性の病気へと進行してしまいます。
膵炎の治療は、血液検査、超音波検査などで診断を確定します。
血液検査では、白血球数、炎症反応の指標となるCRP、肝酵素、アミラーゼ、リパーゼなどの膵酵素の測定を行います。
多くの場合、アミラーゼ、リパーゼの数値が高いと急性膵炎と診断されます。
膵炎の治療として、これまでは数日間の絶食絶水によって膵臓の酵素活性を抑え、輸液療法、抗生剤、制吐剤、鎮痛剤などの投薬をする入院治療が行われます。
また急性膵炎の場合に限り、絶食を行わずに治療可能な犬の急性膵炎向けの新薬ブレンダZと食事療法、静脈点滴を併用するどうぶつ病院が増えてきています。
犬の膵炎の食事は「低脂肪」が条件
膵炎を発症した場合、低脂肪で消化の良い食事と適度な運動が必要となります。
また、おやつなどの間食は避け、バランスの良い食事をとることが大切です。
膵炎は一度発症してしまうと、なかなか完治まではいかない厄介な病気です。
また、再発を繰り返すことが多いため、食事管理の徹底が求められる病気でもあります。
どうぶつ病院から低脂肪の療法食を薦められることが多くありますが、ワンちゃんの好き嫌いが激しい時には、手作り食を選択することも一つの方法です。
手作り食では、魚やささみをメインに使用し、たんぱく質が不足しないように気をつけることが大切です。
また、膵臓の細胞を保護する役割のあるタウリンや抗酸化物質として働くビタミン群、葉酸、カロチン、亜鉛、グルタチオンなどを積極的に取り入れることもおすすめです。
なお、食欲がなく嘔吐を繰り返している時には、吐き気止めの薬を併用した上で、流動食を与えるなどして「何も食べない」状態にさせないように気をつけることが必要です。
サツマイモに含まれる脂質はごくわずか
膵臓は、リパーゼと呼ばれる脂肪分を消化するための消化酵素を分泌する器官です。
そのため、脂肪分の多いフードや食品を食べると、膵臓がこのリパーゼをたくさん分泌し、脂肪の消化を促進させます。
この時、膵臓は活発に働くこととなり大きな負担がかかります。
膵炎のワンちゃんに、低脂肪の食事が必須なのは、このリパーゼの分泌を抑え膵臓に負担の少ない食事が必要となるからなのです。
ワンちゃんの膵炎に役立つ食材であるサツマイモに含まれている100gあたりの脂質はわずかに0.2gで、ブナシメジやキャベツと同じ含有量となります。
これは、低脂肪食が求められている膵炎のワンちゃんにとってうれしい数値。
もちろん、前述のように蒸す・茹でるといった低GI値を保てる調理法を取ることが前提となりますが、ダイエット中のワンちゃんにとっても脂質の少ないサツマイモはおすすめの食材です。
膵炎の犬にサツマイモを与えすぎるのはNG

サツマイモは、食物繊維、ミネラル、ビタミンなどワンちゃんの健康維持に役立つうれしい栄養素がたくさん詰まっている野菜です。
サツマイモにはセルロースとヤラピンという食物繊維が含まれています。
これらの食物繊維は、ワンちゃんの腸内環境を整えるために有効な食材です。
また、サツマイモには抗酸化作用のあるビタミンCがリンゴの10倍と、芋類の中でトップの含有量を誇ります。
その上、サツマイモのビタミンCは熱に強いので加熱しても損なわれることはありません。
この他にも、ビタミンB群、ミネラル、βカロチン、ガンクリシオド、塩分を排出してくれるカリウム、骨を丈夫にするカルシウム、老化を予防する「若返りのビタミン」ビタミンEなど、ワンちゃんの健康維持に役立つ成分がいっぱい含まれている栄養価の高い野菜がサツマイモなのです。
そんなサツマイモは、蒸したり茹でたりすることで低GI食品となりますが、与えすぎることでカロリーオーバーとなる可能性があります。
特に肥満は、膵炎発症の原因の一つとされているため、すでにダイエットを指示されているワンちゃんや太りやすい体質のワンちゃんに与えすぎは禁物です。
理由①炭水化物(糖質)が多いので太りやすい
サツマイモの主成分は炭水化物です。
炭水化物は、大きく分けるとワンちゃんのエネルギー源ともなる糖質と消化吸収されない食物繊維に分けられます。
生のサツマイモに含まれている糖質は100g中29.7gとイモ類の中ではトップクラスの含有量です。
甘くてホクホクしたイメージのあるかぼちゃの糖質は100g中17.1gで、サツマイモと比べるとサツマイモの糖質が圧倒的に多いことがわかります。
また、サツマイモのカロリーは100gあたり132kcal(生の場合、蒸した場合は131kcal)と高めです。
大きめのサツマイモ1本では約390kcalと、脂質の多いドッグフード100gとほぼ同じカロリーまたはそれ以上となります。
ワンちゃんが大好きで甘くて美味しいサツマイモですが、糖質が多く含まれているためカロリーが高く、おやつにプラス食餌のトッピングなどと与えすぎると肥満になる可能性があるため注意が必要です。
理由②食物繊維が多いので消化時間が長い
サツマイモに含まれている炭水化物のもうひとつの成分が食物繊維です。
サツマイモの食物繊維には消化をサポートしてくれる働きがあり、膵炎によってお腹の調子が悪いワンちゃんにとっても有効となる食材です。
食物繊維には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があります。
水溶性食物繊維は、文字通り水に溶ける食物繊維で主に海藻類に多く含まれ、糖質やコレステロールなどをゆっくり吸収する働きをします。
一方、水に溶けない性質を持つのが不溶性食物繊維です。
サツマイモの不溶性食物繊維には、サツマイモにしか含まれていない成分ヤラピンが、腸のぜん動運動を促進してくれます。
このヤラピンとセルロースの相乗効果で腸が刺激され、便秘の解消に役立ちます。
ただし、サツマイモには不溶性食物繊維が多く含まれているため、与えすぎることによって便秘を招く恐れもあるのです。
また、水溶性食物繊維はとりすぎることで下痢をする可能性があります。
食物繊維は膵炎のワンちゃんにとってとても有効な栄養成分ですが、与えすぎることで体調不良を起こしてしまう可能性があるため注意が必要です。
膵炎の犬に与えるサツマイモの量の目安
栄養価が高く美味しいサツマイモは、膵炎の影響で食欲が落ちたワンちゃんにぜひ与えたい食品ですが、生で与えることや与えすぎは禁物です。
また、膵炎のワンちゃんにサツマイモを与える際は、蒸す、茹でるなどしてGI値を低くするためにサツマイモの水分を保てる調理法がおすすめです。
まずは、少量をトッピングやおやつとして与えて、消化不良を起こさないかよく観察してみましょう。
なお、おやつとして与える場合は、1日の摂取カロリーがオーバーしないように、フードの量を減らすなどしてカロリー調整を行うことが大切です。
小型犬の場合
膵炎の小型犬には、ごく少量をおやつやフードのトッピングとしてサツマイモを与えましょう。
また、喜ぶからといってたくさん与えてしまうと、カロリーオーバーや消化不良を起こす可能性があるため注意しましょう。
健康なワンちゃんのおやつの量は、1日に必要なカロリーを10で割ったものが適正量とされています。
10kg以下の小型犬にサツマイモを与える量は、小さめのサツマイモを1.5cm程度の厚みに輪切りにしたもの(約25g、約35kcal)1枚または乱切り3個程度(約30g、約29kcal)を目安に、蒸すまたは茹でて与えましょう。
膵炎のワンちゃんの場合は、運動量が少ないため健康なワンちゃんの必要カロリー量に比べると少なめとなりますが、低脂肪食=低カロリー食ではないため、通常与えている低脂肪フードのカロリーを参考にしておやつの量を割り出してみてください。
中型犬の場合
膵炎の中型犬にもおやつやフードのトッピングとしてサツマイモを与えることができます。
美味しいサツマイモはワンちゃんにとっても嬉しいおやつです。
しかし、喜ぶからといってたくさん与えてしまうと、消化不良を起こしたりカロリーオーバーとなる可能性が高いので注意しましょう。
健康なワンちゃんのおやつの量は、1日に必要なカロリーを10で割ったものが適正量とされています。
20kg以下の中型犬にサツマイモを与える量は、手のひらサイズのサツマイモを1.5cm程度の厚みに輪切りにしたもの(1枚約25g、約35kcal)3枚または乱切り6個程度(約60〜70g、約80kcal)を目安に、蒸すまたは茹でて与えましょう。
膵炎のワンちゃんの場合は、運動量が少ないため健康なワンちゃんの必要カロリー量に比べると少なめとなりますが、低脂肪食=低カロリー食ではないため、通常与えている低脂肪フードのカロリーを参考にしておやつの量を割り出してみてください。
大型犬の場合
膵炎の大型犬にサツマイモを与える場合も、おやつやフードのトッピングとして与えることがおすすめです。
また、食いつきが良いからといってついたくさん与えてしまいがちですが、与えすぎはカロリーオーバーや消化不良を起こす可能性があるため注意しましょう。
健康なワンちゃんのおやつの量は、1日に必要なカロリーを10で割ったものが適正量とされています。
大型犬にサツマイモを与える量は、手のひらサイズのサツマイモを1/2個程度(約100g程度、約130kcal)を目安に輪切りや乱切りにして、蒸すまたは茹でて与えましょう。
膵炎のワンちゃんの場合は、運動量が少ないため健康なワンちゃんの必要カロリー量に比べると少なめとなりますが、低脂肪食=低カロリー食ではないため、通常与えている低脂肪フードのカロリーを参考にしておやつの量を割り出してみてください。
まとめ:膵炎の犬の食事で気をつけること
一度発症してしまうと生涯付き合う可能性が高い膵炎は、低脂肪で消化の良い食事と適度な運動が必要となる病気です。
膵炎を発症した場合には、脂質の多いおやつなどの間食や人の食べているものを与えることは避け、栄養バランスの良い低脂肪の療法食やGI値の低いサツマイモなどのおやつを与えましょう。
また膵炎は、一度発症すると再発を繰り返す可能性が高い病気です。
再発を防ぐためには、初期の段階で発見し治療と食事療法を行うことが大切ですが、体質や生活環境、ストレスなどによって再発を繰り返すことが多いため生活習慣には注意しましょう。
また、肥満も膵炎の原因の一つであると考えられているため、しっかりとした体重管理を行う事も大切です。
関連記事:
犬の膵炎の食事
犬の膵炎にりんごは大丈夫?
膵炎の犬にささみは大丈夫?
参考サイト:
ペット栄養学会詩-膵炎の食事管理
たてやクリニック栄養通信-血糖値が気になる方の『さつまいもが食べたくなった時の食べ方』
一般社団法人日本臨床獣医学フォーラム-急性膵炎
OIMOMAGAZINE-さつまいものGI値は調理法によって変わる!

